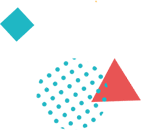「教え惜しむ指導」で学力をヒキダス
「いまの学生のなかには、実験の過程で教科書と違う結果が出てくると、『実験のやり方を間違えた』と言って、その結果を改ざんして持って来る者がいる。昔、我々の時代には、違う結果が出てこようものなら、『やった!新しい結果が出てきたぞ!』と、それが新発見につながるかもしれないというんで、たちまち舞い上がったものですが…」
「いまの学生のなかには、実験の過程で教科書と違う結果が出てくると、『実験のやり方を間違えた』と言って、
その結果を改ざんして持って来る者がいる。昔、我々の時代には、違う結果が出てこようものなら、
『やった!新しい結果が出てきたぞ!』と、それが新発見につながるかもしれないというんで、
たちまち舞い上がったものですが…」
その結果を改ざんして持って来る者がいる。昔、我々の時代には、違う結果が出てこようものなら、
『やった!新しい結果が出てきたぞ!』と、それが新発見につながるかもしれないというんで、
たちまち舞い上がったものですが…」
―元東北大学総長。
―元東北大学総長。
ここには、新しいものを見つけ出そう!ナゾ解きを楽しもう!という学び本来の姿勢は皆無です。
あらかじめ用意された答えに効率よく到達するテクニックとパターンだけを指導された“受験エリート”たちの、なれの果てです。
あらかじめ用意された答えに効率よく到達するテクニックとパターンだけを指導された“受験エリート”たちの、なれの果てです。
ここには、新しいものを見つけ出そう!ナゾ解きを楽しもう!という学び本来の姿勢は皆無です。
あらかじめ用意された答えに効率よく到達するテクニックとパターンだけを指導された“受験エリート”たちの、なれの果てです。
あらかじめ用意された答えに効率よく到達するテクニックとパターンだけを指導された“受験エリート”たちの、なれの果てです。
では、どうすればよいのでしょうか? 一言でいうと、“教えすぎ”をやめることです。辛抱することです。そう、「教え惜しむ」べきなのです。
特に進学塾と名の付く教育機関は、良かれと思ってではありましょうが、総じて“教えすぎ”です。手っ取り早く答えにたどりつく見事な解法を手取り足取りさっさと教えてしまいます。子どもから考える機会を奪っているのです。なぜそうなってしまうのでしょう?
合格という結果を求められるプレッシャー、子どもたちの適性や成長曲線に関わらず、6年生の2月1日までに“合格力”をつけなければならないプレッシャー、模試の成績による一喜一憂、校舎間の競争、そして、思春期にさしかかる子どもたちが起こす想定外の心の変化…理由はいくつでも挙げられます。
しかし、これらは言い訳にはなりません。自戒も込めて厳しく言うなら、すべては、子どものためではなく、指導者が自分のためにやっていることですから。
こんな環境で勉強をした子どもは、自律している一部の子を除いて、主体性を失います。ミスを恐れるようになります。「マニュアル人間」「指示待ち人間」予備軍が多数生まれるようになります。
お子様の合格は、お子様の手柄です。そして、それを一番近くで見守られたご家庭のものです。塾の“先生”のものではありません。塾の“先生”はあくまでもサポーター。決してフィールドプレーヤーではないのです。
ですから、私たちは教え惜しみます。子どもの先回りはしません。ヘルプしません。サポートに徹します。
特に進学塾と名の付く教育機関は、良かれと思ってではありましょうが、総じて“教えすぎ”です。手っ取り早く答えにたどりつく見事な解法を手取り足取りさっさと教えてしまいます。子どもから考える機会を奪っているのです。なぜそうなってしまうのでしょう?
合格という結果を求められるプレッシャー、子どもたちの適性や成長曲線に関わらず、6年生の2月1日までに“合格力”をつけなければならないプレッシャー、模試の成績による一喜一憂、校舎間の競争、そして、思春期にさしかかる子どもたちが起こす想定外の心の変化…理由はいくつでも挙げられます。
しかし、これらは言い訳にはなりません。自戒も込めて厳しく言うなら、すべては、子どものためではなく、指導者が自分のためにやっていることですから。
こんな環境で勉強をした子どもは、自律している一部の子を除いて、主体性を失います。ミスを恐れるようになります。「マニュアル人間」「指示待ち人間」予備軍が多数生まれるようになります。
お子様の合格は、お子様の手柄です。そして、それを一番近くで見守られたご家庭のものです。塾の“先生”のものではありません。塾の“先生”はあくまでもサポーター。決してフィールドプレーヤーではないのです。
ですから、私たちは教え惜しみます。子どもの先回りはしません。ヘルプしません。サポートに徹します。
そして「競争よりも共創」。
少しでも上位の学歴を得、将来の選択肢を確保するために受験を競争とみなし、勝つことを目的とする教育はすでに沈みかけています。
これからの社会は〇〇になるから、そこで活躍する人材にしたとして、主体的な人生と言えるでしょうか?わが子をパーフェクトな人材にする必要はありません。できることを大いに引き出しオンリーワンを実感できること、できないことは周囲と協力して共に創るコミュニケーション能力を培うこと、これこそが共創であり、教育。
少しでも上位の学歴を得、将来の選択肢を確保するために受験を競争とみなし、勝つことを目的とする教育はすでに沈みかけています。
これからの社会は〇〇になるから、そこで活躍する人材にしたとして、主体的な人生と言えるでしょうか?わが子をパーフェクトな人材にする必要はありません。できることを大いに引き出しオンリーワンを実感できること、できないことは周囲と協力して共に創るコミュニケーション能力を培うこと、これこそが共創であり、教育。
身のまわりのことに自ら関心を持ち、自ら知識を活用し、自分流の発想や調査を行える子になってほしい親御様。
他者を理解し、かつ自らを表現し、説得できる力をつけさせたい親御様。
その関門の1つである「受験」という波に、ただ呑まれてしまうのか、それともたくましく乗りこなすのか?
何があっても溺れないよう安易に浮き輪をたくさん用意してしまうのか、
それとも、泳ぎ方を教えるのか?
人生の波は、子どもたちに幾度もやってきます。
受験を通して、お子様が“泳ぎ方”を自ら体得し、自律への一歩を踏み出し、生涯学び続ける力を身に着けられるよう願うのみです。
他者を理解し、かつ自らを表現し、説得できる力をつけさせたい親御様。
その関門の1つである「受験」という波に、ただ呑まれてしまうのか、それともたくましく乗りこなすのか?
何があっても溺れないよう安易に浮き輪をたくさん用意してしまうのか、
それとも、泳ぎ方を教えるのか?
人生の波は、子どもたちに幾度もやってきます。
受験を通して、お子様が“泳ぎ方”を自ら体得し、自律への一歩を踏み出し、生涯学び続ける力を身に着けられるよう願うのみです。